古地図の概要
この首里古地図と呼ばれる首里城下の市街図は、琉球王府の平等所(ふぃらじゅ、首里の番所)で使用されていたと考えられている(東恩納寛惇)。原図は、廃藩置県後は旧首里市役所で保管されていたが、沖縄戦時の空襲で焼失した。
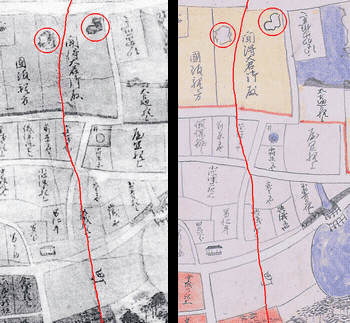
鎌倉のガラス乾板(左)と複製図の比較
(琉球国絵図集成 第1集より引用)
沖縄県立図書館が所蔵するものは東恩納寛惇が絵師の具志に委託して1910年に複製した原寸図で、他に戦災を逃れた複製図は知られていない。
戦後に残された古地図に関する資料として、鎌倉芳太郎が撮影したガラス乾板がある。残念ながらモノクロの部分撮影図であるが、もちろん図形的には正確である。それと県立図書館所蔵図を比較すると若干の歪はあるが、文字の向き・位置・大小関係のみならず修復痕(縦の赤線)や破損部(赤丸)にいたるまでかなり正確に再現されていることがわかる。
首里古地図に限らず、後世の複製図ではその時点での最新情報を知っている作業者による意識無意識の修正や加筆、あるいは美術性を優先した改変が行なわれてしまう事例もあるが、首里古地図の場合は忠実に再現する事に主眼を置いたまさに複製図であると言える。
情報の脱落など手作業による複製の限界も確認されているが、焼失した古地図の色彩情報まで含む全体像を今に伝える唯一の資料である。
首里古地図の作成年代は明らかではなく、城下の屋敷配置、筆頭者名やその役職と文書資料の記録から製作年代を推定する試みが戦前からなされている。しかし、古地図の記載情報が新旧入乱れた時間的幅を持っているため着眼点によって意見がわかれ、東恩納寛惇の1702年~1714年、嘉手納宗徳の1703年~1707年、真境名安興の1715年~1732年などの説がある。
いずれの説も城下の記載情報は1700年代初頭を基本としそれに後代的要素が入り込んだものである点では一致しており、この後代的要素は1850年に行なわれた修復作業の際に入り込んだ可能性が指摘されている(嘉手納宗徳)。

新しい試みとして、測量技術の伝播と古地図の精度および首里城内の殿舎の有無に注目した製作年代推定がなされている。
古地図を現在の地図と重ね合わせると、龍潭池を中心に概ね東西2.9キロメートル、南北1.9キロメートルの範囲が描かれており、その計算上の縮尺は約1/900となる。
この重ねた図から古地図の道路(黒)と現在の道路(灰色)を抽出すると、地図中央の平坦部(A)では現在も残る古い路地と古地図は良く一致している。これは享保年間(1716~1735)に用いられ十字法による成果物、つまり単純に土地の縦横を測った結果と考えるには精度が高い。
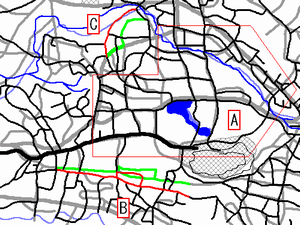
その一方、傾斜地では補正の失敗による誤差が生じている。首里城から金城ダムにかけての南側斜面(B)では、斜面下側(地図の外側)への誤差が発生しておりその誤差は傾斜度に応じて大きくなっている。北側の急斜面、現在の儀保付近では対応する路地の特定すら困難であり、誤差は外側へ発生していると推定される。
この技術的未熟さは、当時、三司官であった蔡温が元文検地(1737~1750)で用いた廻り検地法、いわゆる三角測量法の伝播初期の測量結果であることを示唆している。さらに、城内の殿舎の有無から1729年~1732年の測量と推定することができる(伊從勉)。
この説に従うと測量の時期と記載情報のずれ、つまり記載情報が30年近く古いことが疑問として残される。しかし、図が作成時より古い情報を含むことは時系列に矛盾せず、測量技術の伝播と精度に着目したこの説の合理性を損なうものではない。
製作年代に異論はあるものの、この古地図が300年前の首里を知る重要な手掛かりであることは言うまでもない。さらに、単なる地図ではなく小さな路地や庶民住居に至るまで丹念に書き込まれた絵図でもあり、文書資料からは得られない視覚情報を含む点も貴重である。
