基礎知識
琉球の染織に関する基礎知識をご紹介します
沖縄の染織には古来から伝わる染め、織りがあり、他国との交易、文化的交流の中で多種多様に発展していった。ここでは沖縄に伝わる染織について説明していきたい。
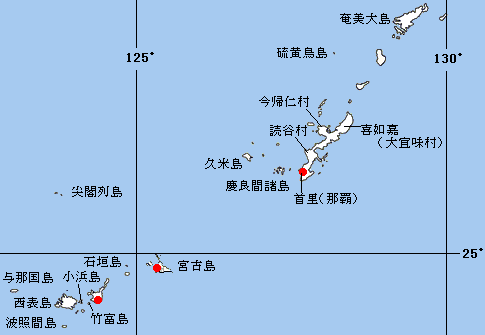
沖縄の染め 紅型
起源

約15世紀頃から存在していたと考えられ中国、朝鮮、日本、ジャワ・スマトラ・パレンバン(インドネシア)、シャム(タイ)などの東南アジアとの交易の中で様々な技法を取り入れ、発展させていったと考えられる。
書物で紅型を指したのではないかとみられるものとして『李朝実録』では"紀白"(1456年)、"彩絵"(1479年)と記され、天順7年(1463年)に朝鮮に派遣された琉球の使節が「琉球の男は斑爛之衣(彩りの美しい模様の衣)を着る」と述べており、『使琉球録』(1534年)には"彩服・彩段"とある。
紅型(または紅型を制作すること)を表す「型附」の文字が初めて登場するのは『尚氏家譜』の(崇禎12年=1639年)、『琉球国志略』(1756年)には「白絹に文様を染める者がいる。また5色を用いて生地を染める者もいて、皆自ら着用している。そして贈物や商売にはおおむね染色しない地色のままの生地を用いる」とある。
他にも『おもろさうし』(1532年)、『馬姓家譜』(乾隆16年=1751年)、『球陽』巻15尚穆王16年(乾隆32年=1767年)、巻16尚穆王31年(乾隆47=1782年)、『使琉球記』(1802年)などに記述がみられる。
名称について
沖縄学研究の創始者である伊波普猷(1876-1947)は『琉球更紗の発生=古琉球紅型解題』(1928年)で染料の原産地であるベンガルから弁柄(ビンガラー)のようであるとし、東恩納寛惇『歴代宝案』の"上水花布(更紗)"がインドのベンガルから渡来したことから紅型の語源はベンガルに由来するとしている。
沖縄戦による焦土の中、紅型の復興に尽力した城間栄喜は「父(栄松)は中国福建省に(びん)という地名があったので型が語源ではないか」と話していたようであり、また職人たちの間では元来、型染のことを"型附(カタチキ)"と呼んで、色を差すことを紅(ビン)を入れると言っていた。
また『古琉球紅型』『沖縄文化の遺宝』の著者で型絵染作家の鎌倉芳太郎(1898-1983)が沖縄で紅型調査を行った大正末年の頃、首里の紺屋(染屋)では「ビンガタ」と呼んでいたので「色彩のことを称して紅、文様を指して型という」が語源であると考え、現在では色彩を称し紅、文様を型とする意味で紅型という名称が使われている。
紅型の用途

王族の礼装・日常着、中国皇帝の冊封使節を歓待する際少年達が着た「御冠船踊(うかんしんおどり)」などの踊衣裳、特別な場合のみ許された庶民の晴れ着、神衣裳の他、資源の少ない琉球では外貨獲得のため中国への貴重な貢品として作られていた。(『使琉球記』嘉慶7年(1802年)に"東洋花布"の名で記される)
職人たち
紅型を作る職人は紺屋と呼ばれ、首里、那覇に多数いたと考えられる。その中でも首里に住居をかまえ王府の絵図奉行の絵師(中国で4~5年絵の修行をした)の下、紅型を制作したのが紅型三宗家といわれる3家である。
最も歴史があり王家の龍譚の水を使用できた沢岻家、中国から唐紙の技法や印金紙・緞子紙を学んだ知念家、城間家であり、王族、按司、親方、親雲上(ぺーちん)、に次ぐ階級の筑登之(ちくどぅん)の位を与えられ士族以上の階級が着用する紅型が作られた。
首里で作られた紅型の他に浦添型(印金手法を用いた摺込みによる型付け法で色料の固着剤に蒟蒻粉を使うことから蒟蒻型ともいわれ、朧型とともに後に首里に住居を移す沢岻家に代々伝えられてきた紅型の起源と考えられる手法)、那覇型(17世紀商都那覇で作られた庶民階級の着ることが出来る紅型。泊型ともいい、首里型と違い文様・色が制限されていた。交易品としての紅型も含む)がある。
型紙
型紙は柿渋を引いた紙に、豆腐を乾燥させたルクジュウを下敷きにして型紙を彫るが、模様の部分を彫り残し、周りを糊で防染する白地型と、模様の輪郭線のみを線彫りし糊で防染する(1回の型置きで地染めが可能な)染地型があり、型紙の大きさによって大模様型(奉書紙の全紙1枚)、鎖大模様型(奉書紙を3枚1組に連続させた絵羽状の模様)、三分二中手型(奉書紙の2/3)、中手模様型(奉書紙の1/2)、中模様型(奉書紙の1/4)、細模様型(奉書紙の全紙1/4の大きさで細かい模様)と分類される。
また、用途による名称もあり庶民が還暦以上の祝いに着用が許された祝型、庶民の死装束に用いられた後生(グソー)型、航海の安全を祈願する大船型、ガンジ型、タンナ型、旅ふい型、ビルイ型、御冠船型と、階級による名称では御殿型、殿内型、若衆型がある。
紅型には型紙を用いる型染の他に舞台幕や「うちゅくい」と呼ばれる風呂敷など大きな布を染める技法として、糊を入れた口金つき絞り袋(布)で糊防染する筒引き(筒描き)がある。染色にも藍(少量の墨)のみを使用した藍型(えーがた)、藍型を主に複数の色彩を染め入れた紅入藍型(びんいりえーがた)、沢岻家に伝わる複数の型紙で模様を染め重ねる朧型(うぶるがた)があり、朧型にも藍朧型、紅朧型など多様な制作方法がある。
工程
白地型の型紙を使った方法
(模様を染めた後、糊で模様の部分を伏せて地染めする返し)
型彫り(紗張り)→地張り→型置(型付)→地入れ(豆引き)→色差し(下塗り・1度摺り)→色差し(上塗り・2度摺り)→隈取り→(蒸し)水元→糊伏せ→地染め→(蒸し)水元→完成[筒描き・染地型の型紙を使った方法]型彫り(染地型の場合)→地張り→筒描きまたは型置→地入れ(豆引き)→色差し(下塗り・1度摺り)→色差し(上塗り・2度摺り)→隈取り→(蒸し)→糊伏せ→地染め→(蒸し)水元→完成
素材・色・模様について
布地は木綿、苧麻、芭蕉、絹、桐板(トンビャン)などが身分、用途によって染められていたようである。地色は約20色あったとされ白地、黄色地、水色地、花色地、緑色地、葡萄色地、藍(深)地、青藍地、段染地(染め分け地)などである。主に王族・士族婦人などの女性、または元服前の王族・士族の少年、王府に仕える小姓などが着用し、黄色は王族婦人の礼装、水色・浅地は日常着、花色・白と季節や年齢に応じて着用された。藍型、朧型は第6階級の庶民(地方の町方、農村や諸島の支配階級に属する婦人たち)にも着用が許されていたとされ階級によって着用できる地色が決まっていた。
模様の彩色には主に顔料を用い、顔料の上から染料を重ねたり、染料に顔料を重ねたりしながら彩色をし、その後朱色以外の模様に隈取りを施し模様に立体感を与えた。紅型では季節に関係なく春を現す桜に冬の梅、秋の楓の紅葉、雪輪など春夏秋冬の模様が同時に存在することも大きな特徴で、うっそうと樹木の茂った緑濃い首里では楽園を思わせたことだろう。模様も中国、日本の柄がほとんどで龍、鳳凰などは王子・王妃にしか許されず、身分の高いものほど大きな模様で老人は小さい模様を着用した。
材料は自国でとれた福木、琉球藍などの他、主に中国から取り寄せた顔料・染料が使われほとんどの色料を中国に頼っていることから、当時の琉球と中国との密接な関係がうかがえる。
紅型の衣裳に植物染料だけでなく絵画に使われる顔料を用いたのは、沖縄の強い日射しの中、褪色せず遠くからでもわかる大きな模様を身分の高い人物が着るという(日本の鮫小紋などの手が込んだ細かな細工が高級とされた文化と違って)衣服でありながら「着る」というより「見せる」絵画として、観賞されるべきものとしての表現を持つ、独自のおおらかな自然美を表したかたちになっていったと考えられるのではないか。また、琉球で多様な織物が存在していたことにより、紅型が現在まで華やかさを失うことなく伝えられた一因とも考えられる。
沖縄の織り
素材
沖縄には他県では類をみないほど多様な織物が存在する。素材には、苧麻、芭蕉、絹、木綿、桐板など多くの種類を使用し、用途に応じた織物を織っていた。岡村吉右衛門『南国沖縄 光と技』によると、苧麻は日本経由で栽培され、芭蕉はインドネシア語のバナナを指すピサング(沖縄方言でヒイシャグ)に似ることから、南方経由で持ち込まれたとされる。絹は日本、紬用の長繭は南中国系を起源と考えられ、木綿は儀間真常が1611年に薩摩から種を持ち込んだという記録がある。
また、現在では幻の織物とされる桐板(トンビャンまたはトゥンビャン・トンバン)についても特に説明する。
桐板は琉球王府時代から戦前まで用いられていた織物素材で中国から輸入されていた。中・上流階級の間で使用され、繊維は非常に透明でハリがあり、ケバがほとんどなく撚りをかけずに織られるのが特徴で、独特のひんやりとした触感があり夏用素材として珍重された。糸が撚りつぎで作られていることにも特徴がある。この東恩納寛惇文庫『琉球染織』資料には、桐板を使用した織物が多く収集されており、桐板の利用状況を知る上で貴重な資料である。
染料には藍、ハチマチバナ(紅花)クール(紅露)、鬱金(ウコン)、テカチ(車輪梅)、グールー(サルトリイバラ)、楊梅、福木、ユウナ(オオハマボウ)、梔子、日本・海外との交易による蘇木、臙脂など主に植物染料を用いていた。
技法
織の技法では、中国から浮織、両段織、絽、南方から絣、花織、日本から紬を取り入れ、読谷山花織(ユンタンザハナウイ)、絣織物、首里の織物[花倉織、花織(ハナウイ)、ロートン織(道屯織)、手縞(ティジマ)、ムルドゥッチリ(諸取切)、花織手巾(ハナウイティサージ)、煮綛芭蕉(ニーガシバサー)]、宮古上布、八重山上布、久米島紬、与那国花織、ミンサー、手巾(ティサージ)など地域によって個性豊かな美しい布を現在でも織っている。
衣冠定(衣服定)
織物は紅型と同様、柄の大きなものほど身分の高い人物が着ることができた。着物の幅に絣が1つある1玉(絣の単位)は王家、身分が下がるにつれ玉数は増え、庶民は主に無地や細縞、8玉以上の小さな絣などを着用した。
貢納布
1609年の薩摩侵攻後は王府と薩摩の二重の支配の中で貢納布制度が発展していった。琉球王国は薩摩への貢納品として上布、下布が宮古、八重山へ課せられた。1637年には宮古・八重山に人頭税が課せられ15~50歳の女性は税として布を納めた。村々に機織屋が設置され真っ暗な小屋の中、織女に指名された女性達は役人の厳しい監視の下、1903年まで過酷な労働を課せられた。(笹森儀助の『南島探検』に織屋の記述がみられる。)この貢納布制度により織られた上布は薩摩に渡った上布は薩摩上布の名で流通した。
御絵図
宮古、八重と久米島の女性たちはきびしい生活の下、皆機織りをして家計を支えていた。貢納布に加え王府の絵師が描く「御絵図(みえず)」といわれる絣を中心とした織手本が各産地に渡され、原図通りに糸をつくり、染め、機に向かい布を織ることを強いられた。貢納布と御絵図によって島々の女性たちはおおいに苦しめられたが、反面各地に特徴あるすばらしい織物文化が育ち、その結果として現代に伝えられていることも否定できない。
代表的な沖縄の織物
芭蕉布

糸芭蕉を原料とした織物で、芭蕉布と思われるものでは『歴代宝案』に16世紀後半には貢物・貿易品として芭蕉「細嫩蕉布(サイドンクンプ)」の記述がみられる。『李朝実録』には久米島に漂着した朝鮮人(1456年)、与那国に漂着した朝鮮人(1477年)が芭蕉を苧と表現していたようである。万暦26年(1598年)尚寧王が朝鮮に「土物夏布、芭蕉二〇匹」を贈ったと記される。
16世紀には中国への貢物や貿易品として使用され、1609年の薩摩の侵攻以後、薩摩は琉球に対し貢納品として芭蕉布3000反を義務づけた。また、芭蕉布を"上夏布"として南方諸国へ輸出することによって絣や花織の技法を持ち帰ることができたと思われる。
染色は植物染料で、藍、赤茶色のテカチ(車輪梅)、琉球王国では公の場で着る朝服(官服)、婚礼衣裳、喪服、神衣裳などにも芭蕉が利用されていた。身分によって使用する繊維の太さが違い、王族は幹の中心部に近い上質で細く柔らかな繊維で織られた芭蕉布を着用していた。
糸芭蕉は沖縄の気候に適していたためよく育ち、沖縄各地で栽培され、織物用の糸として利用された。戦前は喜如嘉(山原)、今帰仁、首里(煮綛芭蕉)、竹富島、小浜島、与那国島などの芭蕉に特徴がある。芭蕉は着ごこちがよく王族から庶民まで幅広く着用されていた。
読谷山花織(ユンタンザハナウイ)
15世紀インドなどの南方系から伝わったと考えられ、『歴代宝案』成化6年(1470年)に琉球が「棋子花異色手幅 二条、彩色糸手幅二条、綿布染手幅 二条」を朝鮮に贈ったことや、成化16年(1480年)シャム国から琉球国に「手幅織花糸黄布一条」が贈られたと記されているが、直接読谷山花織に結びつく記述は少なく詳細は不明である。
読谷山花織は綿を素材にした浮織の一種で、綿衣(ワタジン・袷の着物)、胴服(筒袖の短衣)に使用された。紋綜絖(花綜絖)による緯浮の"ヒャイバナ(浮織)"技法で、模様は藍地に白・赤・黄色・緑の緯浮糸で織られ、模様を花に喩え花織といわれる。現在では着尺と帯として約30種類の花模様があり、基本柄としてジンバナー(銭花)、カジマヤー(風車)、オージバナ(扇花)が知られる。
読谷山手巾(ユンタンザティサージ)も織られており、紋綜絖(花綜絖)による経または緯の浮織による"ヒャイバナ"と、経糸を竹ベラですくい色糸を縫い取り模様を作る"ティバナ(手花織または縫取織)"の二つの技法を使っている。
手巾とは本来女性が肩や髪にかける手ぬぐいであるが、女性が愛する男性のため思いを込めて織ったウムイティサージ(想い手巾)と、兄弟が旅に出るとき旅の安全を願い姉妹(沖縄では古くから女性は家族の守り神と考えられていた)が織ったウミナイティサージ(姉妹手巾・祈り手巾)がある。
那覇の絣織物
15世紀前半タイ・マラッカ両国王から絣を贈られたことが『歴代宝案』に記されていることから南方伝来とする考えと、図柄の展開が中国のものに似ているということから中国説があり、起源ははっきりしない。
絣の図柄はトゥイグヮー(鳥)、ブシ(星)、バンジョウ(番匠)、トーニー(田舟・養豚のカイバ桶)、ウシヌヤーマ(牛馬耕の鋤の手)など生活に関わる身近なものを題材に構成されていた。絣は染色しない部分をあらかじめ別の糸でくくって防染し、染色する。その後、くくった部分をほどく。この糸を使って織ると絣模様を織り出すことができる。くくる方法以外に絵にそって種糸を掛け、墨で印をつけ、その部分を手くくりする技法の絵図絣という技法もある。絣には経絣、緯絣、経緯絣があり幾何学的な柄を組み合わせて織られることに沖縄の絣の特徴がある。
琉球絣とは本来沖縄各地(戦前の那覇の産地は泊、小禄、崇元寺など)で織られる絣の総称だが、戦後、南風原で絣織物を復興させ主要な産地となったことから、南風原で織られた絣を琉球絣というようになる。現在は主に絹を素材に織られている。
首里の織物
王都首里に生まれた織物で紋織などを使った美しい織物。花織に関連する資料として、『球陽』6巻、尚質王12(1659年)首里の国吉が進貢使とともに中国に渡り浮織を学んだことが記されている。
変化に富んだ多様な織が特徴で、花倉織、花織(ハナウイ)、ロートン織(道屯織)、手縞(ティジマ)、綾の中(アヤヌナーカー)、ムルドゥッチリ(諸取切)、花織手巾(ハナウイティサージ)、煮綛芭蕉(ニーガシバサー)などがあり、首里で身分の高い人々に着用される織物であった。
王府内では織の技術の高い地方の平民の女性を選び「布織女」として御用布の製作にあたらせた。また、士族階級の女性が家族のために織ったともいわれ、王妃や王女なども糸を紡ぎ機に向かっていたようである。
絽

2本の経糸を交差させて織る技法。交差させた部分の緯糸に隙間があき、紋様となる。
花織(ハナウイ)

緯糸が表に浮き経糸が裏に浮く両面浮花織のことで、両面使用できるのが特徴。
花倉織
絹を使い絽織と花織が市松模様に織られ、王妃・王女や祝女(ノロ)の最高位である聞得大君が着用していたとされる特別な織物。
ロートン織(道屯織)

中国から伝わった紋織布の両面とも経糸が浮く両段織で、主に上流階級の男性の着物として織られた。
手縞(ティジマ)
絹や綿を使用した織物で、2色の撚糸を施した複雑な格子の中に絣を構成した織物。
ムルドゥッチリ(諸取切)

すべて(ムル)絣(トゥッチリ)の意味。ほとんどの経糸、緯糸が絣糸で構成されている。「御絵図(みえず)」に多数みられる経緯の色絣など特徴的な織物。崩れ格子(クジリゴーシ)ともいわれる。
煮綛芭蕉(ニーガシバサー)
芭蕉の柔らかい芯部分を使って灰汁で漂白し、様々な色に染色したもので官服、絽織などにされた。(糸の染色には首里にある紺屋を利用していた。)糸は撚り継ぎで作られていた。
花織手巾(ハナウイティサージ)
縫取織の技法で絣、縞を組み合わせた手巾。他の地域の手巾と同様、夫や兄弟のお守りの他、外国への贈答にも用いられた。ほかに縞と縞との間に絣を入れた綾の中(アヤヌナーカー)などの織物もみられる。
宮古上布
苧麻(方言でブー)を原料とした織物で、宮古上布の起源は稲石という女性が、進貢船を難破から救った夫の昇進に感謝し、尚永王に「綾錆上布」といわれる布を織り、献上したことにはじまる。苧麻などの繊維から糸をつくることを績む(うむ)という。
染料には藍を使用した紺地の上布が特徴である。絣模様を1本1本指先で揃える緻密な柄が織られた。明治期に奄美より締機を用いた絣技法が導入され、細かな十字絣の「蚊絣」による宮古上布が織られるようになった。
八重山上布

起源は定かでないが、薩摩の貢納布のため織られたことがはじまりと考えられる。宮古上布同様厳しい人頭税の下、八重山の女性達も過酷な労働を課せられた。貢納布として宮古島は藍地・八重山は白地を織るよう指定された。
原料は苧麻で絣は手括りのものと、染料にクール(紅露)を使い刷毛で直接糸に摺り込む(捺染)摺込絣がある。仕上げに海水に晒す海晒しによって白地はより白く、絣の色はより濃く仕上げられる。
久米島紬

絹を原料とした織物で、15世紀頃堂之比屋が中国から養蚕技術を学び伝え、『上江洲家家譜』、『琉球国旧記』(1731年)によると万暦47年(1619年)越前の宗味入道(琉球名:坂本普基)が沖縄に渡り、尚寧王の茶道職を勤める傍ら養蚕技術を得ていたため王の命により久米島に養蚕技術を伝えたとされる。
他に『仲里旧記』(1706年)、『琉球国由来記』(1713年)、『琉球国旧記』(1731年)、『具志川旧記』(1743年)に久米島紬に関連する記述がある。
久米島紬の染料はテカチ(車輪梅)、グールー(サトリイバラ)を泥媒染したもので仕上げに砧打ちで風合いを出す。焦茶色の地色が一般的だが、上江洲家の御用布裂地帳によると王府時代の久米島紬(御用布)には、ユウナを使ったグーズミ染めによる灰色絣や地色に紅・黄色・藍など多くの色も存在していた。
ミンサー
ミンサーとは綿(中国語でミン)、狭(サー)で、綿狭帯の細帯を指す。
沖縄では古来から衣服の着用に帯は用いず、腰紐に着物を押し込むウシンチーという着用法が一般的であるが、厳しい労働に従事する庶民は着物が解けないよう藁帯などの帯をきつく締めていた。田舎は自由恋愛による婚姻制度であったため、女性が想いを寄せる男性に帯を贈り、モーアシビ(毛遊び・若い男女が月夜の下、農作業後に野原に集い三味線に興じ唄い踊る出会いの場)で男性が女性から贈られた帯を締め、互いの愛情を確認しあう証として織られていた。男性は結び目を後ろにし、女性は前で結んでいた。
竹富島の竹富ミンサーや小浜島の小浜ミンサーは絣が5つ玉と4つ玉が1対で、配偶者となる男性に「いつの世までも末永く.....」という願いを込めて贈られた。帯の両端の縞はムカデ文様で「足繁く通う」という意味であるが、いつ頃からこのような柄が織られていたか不明である。
柱に糸を結びつけ織った花柄が特徴的な読谷山ミンサー、藍染の無地のミンサー、那覇ミンサー、綾中に鳥くずし絣文様の与那国ミンサーなど沖縄各地で細帯が織られていた。奄美大島では、女児の織り遊びとして、細帯が織られていたという記録がある。
与那国織
『李朝実録』(1477年)に与那国島に漂着した朝鮮人が、与那国や黒島では苧麻で布を織り染料には藍を用いていると記されており、15世紀後半には織物が存在していたようである。
原料は苧麻、芭蕉、木綿、絹などで絣はほとんど見られない。苧麻に木綿などの経縞格子など庶民の仕事着となる与那国ドゥタティ、10種類もの花柄を幾何学に織る与那国花織、経縞の中に夫婦を白絣で現すミンサー織の与那国カガンブー、緯糸を織り柄を浮き出させる手巾の与那国シダディがある。
